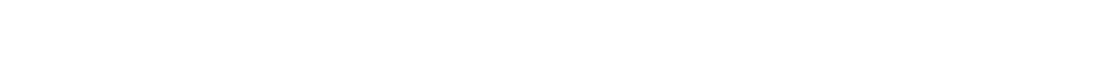ブックオフで知らない世界の扉を開ける
タイトルで絶対に買わないだろうなという文庫もある。まさしくこれがそう。しかし、背表紙のタイトルを見て、本棚から抜き出してしまった。その理由は簡単。そこがブックオフの1冊100円のコーナーで、しかも旅の文庫が集められたエリアだったからだ。
ブックオフの100円コーナーは、見知らぬ作家との出会いの場として、最近お気に入りの場所だ。一冊きりのお付き合いに終わる作家もいれば、作家名をAmazonで検索してお取り寄せしてしまう関係になることもある。100円ではいまや、缶ジュース一本も買えない(幼い頃、スチール缶のコーヒーやジュースは100円だったけれど、今の若い人には分かってもらえない、かな?)。ちょっとお試しするには、ちょうど良いプライスなのだ。
本題に戻ろう。この文庫は、きっとパリの小洒落たグルメな食事の数々が紹介された内容ではない。「メシ」とタイトルにつけたからには、オシャレな雑誌のパリ特集に出てくるような料理店が紹介されているだけではないだろう。パリのB級グルメかもしくはもっと違う何か……、そんな予想を立てながら100円で売られている文庫が並ぶ書棚から抜き取ったのだ。
とりあえずカバーに書かれた本の紹介を読む。パリに住む日本人10人にインタビューし、その生き様が描かれているものらしい。「メシを食う」は、「生活の糧を得る」つまり、パリでしっかり稼いで暮らしている人のことだ。
これならちょっと面白そう。ということで、お買い上げカゴに放り込んだ次第。
もちろん、こうしてお試しに購入されたその他の文庫と同じく、しばし積読されていたことはいうまでもない。最近、食に関する文庫を読んでいたこともあって、その流れで手に取ってしまったのでした。
紹介される10人すべての言葉を紹介することはできないので、気になったフレーズのいくつかをピックアップ。
モノクロームフィルムで撮る写真家の矜持
いや、フィルムってメディアとして、もう完成されているんです。特に白黒フィルムのテクノロジーっていうのは一九五〇年代で止まっているんです。これ以上進化がないんですね。だからこそ白黒フィルムの写真は百年後にも残っていくものだと思うんです
(P100)
パリで活躍している写真家の言葉。写真家になるためにパリに渡ったのではなく、学問するためにロンドンに留学し、気がつけば写真を撮ることでメシを食っていたという。
仕上がった写真に思想があるかないか、実はそこに教養があるかないか、文化というバックボーンを持っているか否か、が関係してくるのはあまり語られない。
写真を撮る技術だけならば、学べば誰でも習得することができる。だからカメラマンにはなることができるが、写真で表現する写真家になれるかというと、それは別問題だ。
フィルムしかない時代、写真を撮るためには、それなりの技術が必要だった。暗室で印画紙に焼きこむのも、やはり技術が必要だし、これには感性も求められる。
しかしデジタルカメラがこれだけ普及した今、ただ写真を撮るだけならば、もはや誰でもできると言っていい。それこそスマートフォンでも考えられないくらい明瞭な写真を撮ることができる。
そんな時代だからこそ、モノクロームのフィルムで撮影することに意義がある。
ここで紹介された写真家は、パリの街角で市井の人をモノクロームのフィルムに収め、後日焼き付けした印画紙をプレゼントするという。貰った方は嬉しいに違いない。そしてその渡された印画紙に焼きこまれた表情は、自分の知らない穏やかな、幸せな表情をしているに違いない、そんなことを想像してしまうエピソードだった。
ポートレートは、誰が撮っても変わりないと思われがちだが、実は撮る人の思想や性根が不思議と反映されるものだ。同じ人を撮っても、意地悪な人が撮ると意地悪な表情に、優しい人が撮れば優しい表情に撮れてしまうのだ。だから、著名人になればなるほど、誰に撮られるかを気にするのだろう。
正しい世界で勝負する
仕事にはすごく満足している。やりがいを感じている。日々のレベルの仕事ではつまらないこともたくさんあるけどね。下らないことに時間使ったり。でも結局仕事なんてどこで働いても一緒でしょ。毎日メールを書いたり電話をしたり。でも違いは結局自分がやってることが何に貢献しているか。日々やってることはしょうもないことでも、それが何か大きなものにつながっている。自分は確かに正しい世界にいるってことが大切。だからずっと働きたかった組織にこられたのは幸せだな。自分たちは世界の流れのトップにいるっていう感覚はすごいよね
(P254)
恋愛に対して自分の心の声に素直に従ってきたら、いつのまにか国連に勤め、メシを食えるようになった女性の言葉。
版元をいくつも渡り歩いていると、結局どこにいても同じであることがよく分かる。
よく人や環境のせいにする人がいるが、大切なのは自分が妥協せずに仕事を全うできているかどうかだ。自分に厳しく人に優しければ
、気がつくとスタッフにも恵まれ、実力以上の作品(雑誌)に仕上がる。
ただし、国連で働く彼女が言っているように、「自分は確かに正しい世界にいるってことが大切」だ。企業で働くサラリーマンである以上、自分が帰属する企業(版元)に倫理観が欠けていたら、どんな仕事(雑誌)を達成(発行)しても、残るのは虚しさだけだ。
自分にここ数年の仕事に対してどうだったか尋ねてみると、残念だが虚しさだけが残ってしまった気がしてならない。
最後に残るのは、誠実さである
お客様に対して、花に対して、自分自身に対してとことん誠実でした。私は、彼の仕事に対する姿勢に、商売というものは自分の技術に対して、人が喜び感動してくれて、その代わり代金をもらうという、とてもシンプルな、原点のようなモノを感じました。やっぱり本当に人の心をつかむのは表面的なことではなく、シンプルなものなんだと
(P316)
パリのような厳しい審美眼をもつ都市で、フローリストとして認められるのは、並大抵のことではないだろう。この言葉は、そのパリで認められたフローリストの妻の言葉である。
表面的な美しさだけではなく、そこに人に喜んでもらうという誠実さがあってこそ、パリでメシを食えるようになったのだ。
私が作った雑誌を手に取った読者が喜ぶような、ためになるようなものを果してここ最近作っているだろうか。誠実に雑誌を作っているだろうか。
そう考えると、やはりちょっと自信がない。自分が編集長ではなく、パートで担当している雑誌ならなおさらだ。新しいスタイルの提案も、読者が本当に知りたい知識や情報も、そこにはない。読むに値する文章、読み応えのある文章ももちろんそこにはない。
日本にいれば、なんとなくメシを食っていける。汚れた世の中に染まって、それなりに生きていくことができる。
そんな生き方も否定はしないけれど、自分がそうであっていいとは思わない、というか、最近そうだったなぁ……と、ハッとさせられてしまった。
このままではマズイ……、相当にヤバイ。
ということで、キレイサッパリ相殺することにいたしました。
もうこの歳になって、パリやミラノやマドリードやロスでメシを食うなんて考えにも及ばないけれど、まだ東京で美味しいメシを食うことを考えることはできる、と思った一冊。
丹念に対象者と付き合って(向き合って)書かれたドキュメンタリーって、やっぱりいいね。
『パリでメシを食う。』川内有緒/幻冬舎文庫