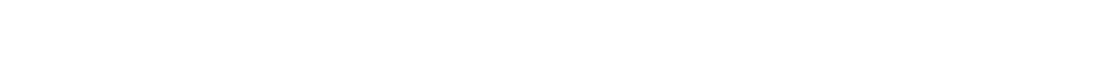文庫とは運命共同体なのです
文庫との出会いは一期一会です。そして、常に自分の運命に呼応するかのような文庫にめぐり逢うのです。
十代の頃、大学の頃、結婚前の頃、こどもが誕生する頃……。いま振り返ると、常にそのときどきの自分にぴったりの文庫に出逢ってきました。
少し前に初めて蔵前さんの文庫を読んで、彼の半生を知りたくなりました。そこでAmazonでポチったのが本日の文庫です。
いつまで僕は雑誌を作り続けられるのだろう。いや、いつまで作り続けるべきなのだろう。
(P387)
自問した。
その答えはすぐには出ないが、いつまでもつくり続けるわけにはいかないことだけは確かだ
四十を超える頃から常に自問自答していた命題。
それは、「いつまで雑誌を作り続けることができるだろうか?」というものです。
最初は、「自分の美意識(こだわり)に叶う雑誌をいつまで作り続けることができるだろう」というものでした。
それが、あまりにも多忙になりすぎて、「いつまでこのペースで雑誌を作り続けることができるだろう(過労死しないかな?)」に変わりました。
そして、「そもそも雑誌をいつまで作り続けられるのだろう」に変わり、「自分がいま表現したいものは、雑誌という媒体ではなく、もっとほかのメディアの方がマッチしてない?」に変わりました。
映像の演出をしていたとき、仕事がすごく楽しく、監督やスタッフにとても大切にされ、仕事自体に不満はありませんでした。
しかし、自分が表現するメディアとして考えたとき、映像ではなく紙媒体、それも雑誌がそのときの自分にあっていると判断し、転職した経緯があります。雑誌業界に入ってからは、版元を渡り歩きましたが、それは自分の理想とする表現により近づくためであって、転職ではなく転社でした。
終わりは始まりでもあるのです
そして、ようやく休刊すると決めた。それはフリーの仕事をいったんやめて、旅に出たときの心境とも似ていた。あのときも、旅から帰国後どうなるかなにもわからなかった。だが、それをやめたことで新しい道が開かれたのだ。まだ若かったからということもあるが、なにかをやめたからといって、することがなくなるということはない。また新しいなにかが始まるだろう。
(P388)
きっと、給与や福利厚生の面で素晴らしい版元に勤めていたら、20代の頃のように、自分の心の声に忠実に行動できなかったでしょう。ぬるま湯に浸かって、ジワジワと衰退していくのを肌で感じつつ、その頽廃的な状況に甘んじていたと思われます。ジョージ・ブライアン・ブランメルのように。
しかし、幸いにもそうではない版元ですので、頽廃的な雰囲気を享受することもままならず、なんとかしなきゃな、というモードに。
でも、これまでの経験で分かっていたのです。蔵前さんの言う「それをやめたことで新しい道が開かれたのだ」と言うことが。
つまり、見る前に跳ぶことが大切だと。
そういえば、結婚式の半年前に無職でしたし、結婚後もステップアップする前に無職の時期がありました。
若い頃(父親になる前)は見る前に跳んでたなー、と。
でも、やめたこと、手放したことで、本当に新しい道、新しいものが手に入るのです。
この歳になると、見る前に跳ぶという行為ではなく、決意することでも同じく道は拓けるということもわかりました。
決意することでも、新しい何かが始まるけれども、そのためには、常に牙を磨いておく必要があるとわかった一冊。少なくとも読書ぐらいしてないと、ほんと思考が錆びてしまいますね。
『あの日、僕は旅に出た』蔵前仁一/幻冬舎文庫