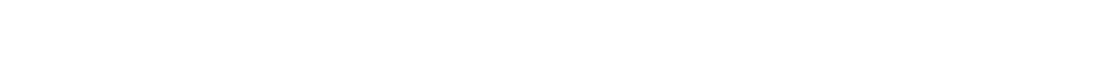日本男児、おっぱい星人がデフォルトです
学生のころから、周りの友人たちに「おっぱい星人」が多いように感じていましたが、実はこの現象がいわゆるデフォルトであることがわかりました。そりゃあ、私の周りにおっぱい星人が多いはずです。
へぇぇー、巨乳好きなんだねー、と感心するばかりで、おっぱいネタにはほぼ関心がありませんでしたが、この世のオトコはほぼおっぱい好きなのです、たぶん。
そういえば、大学生の頃に、宮沢りえやマドンナの写真集が社会現象になりましたが、どうしてビーチクが見える見えないに世の男性が一喜一憂しているのか、不思議でした。
そうしたこの世とのズレを一気に解消してくれたのがロミのこの文庫です。
ロミの書いたこの文庫の効用はほかにもあります。ヨーロッパ人に対するコンプレックスの幾分かをなくすことができます。そうした意味でも一読しておく価値があるといえるでしょう。
たとえばこんな具合です。
キリスト紀元一三三二年のこと、代数学に夢中になったある詩人が、「婦人に見られる七十二の美」という複雑な一覧表を作った。そこには女性の美点が三つずつに分けられて列挙されていたが、かの詩人に言わせると、三という数字は三位一体の数字であると同時に、女性的なるものをあらわす数字であった。
(P34)
「婦人」とか「美」なんて書かれていると、なるほどふんふん、といかにも高尚なことが書かれているように思いますが、ここで「三つの固きもの」として挙げている中に、「支柱のごとく固き尖端」として乳房が挙げられています。下世話な現代日本の週刊誌風に置き換えると「イケてる女の72のチェックリスト」のなかに「ツンと上を向いた乳首」という項目が設けられていると考えるといいでしょう。つまり、高尚でもなんでもない、どうでもいい話題だったりするのです。
とはいえ、おっぱい以外の残り71のリストが気になります。よくもまあ、そんなにたくさん集めたもんだと。結局、女性をモノとしか見ていないということなんですけど。
さらに時代が下ると、より理想的なおっぱいについて詳しい記述が出てきます。
「人体形態理論」でルーベンスは理想の乳房についてこう説明する。「ふくよかにして統一のとれた、すこし上向きの、こころもち外に開いた丸い乳房。ぶよぶよでもぐにゃぐにゃでもなく、慎ましげながらつんと前に出た乳房」。この白くて豊満な、母親を思わせるフランドルの乳房はそのまま美しいエレーヌ・フルマンの乳房に通ずる。ルーベンスは再婚相手となった姪のエレーヌ〔実際には、最初の妻イザベルの妹が結婚した男の妹がエレーヌ〕を、何度も胸をはだけた姿で描いている〔二人の妻の肖像は多数あるが、とくにエレーヌの肖像は名作の呼び声が高い。再婚当時画家五十三歳、エレーヌ十六歳〕。
(P58)
女性の裸を描くためには、ルーベンスの中でおっぱいの基準も必要だったことでしょう。とはいえ、エレーヌと結婚して六十二歳で亡くなるまでの9年間に、ルーベンスはエレーヌとの間に5人の子どもをもうけるとは、飽くなき探究心と言うべきか、ただの色欲ジジイと言うべきか……。
とはいえ、形態的に女性がどのように表現されていたかは、私の当初の卒論テーマだったので非常に関心があります。巨乳は多産の象徴であり、繁栄の象徴でありました、太古の昔は。
(男性に)好まれたおっぱいの大きさや形は、時代によって変化します。
19世紀や20世紀にもヨーロッパではふくよかな乳房がもてはやされました。まあ、当時の絵画その他を見れば、今よりふっくらした体型が美の基準だったんだろうな、くらいのことはすぐに理解できますが、そうした時代によるおっぱいの価値観の変遷を知ることは大変に興味深いものです。
ふたつの傾向がぶつかり合った。大多数の人びとが、花模様をあしらった絹のコルセットで持ち上げられたふくよかな乳房を夢見ていたとすれば、耽美派といわれる人びとは、青緑色の眼をしたスフィンクスかキマイラのような、いわば彼らの文学的理想に合致した両性具有的な乳房を理想とした。一九〇〇年の夏、耽美派と豊満派の対立は結局豊満派の勝利に終わる。斬新なデザイナーたちが平らなシルエットを打ち出し、消え入りそうな痩身をよしとする傾向が、豊満な体型を是とする傾向と衝突したが、耽美派は激しい非難を浴びたのである。
(P156)
耽美派とは、ぺちゃぱいのことを意味し、豊満派とは巨乳ちゃんのことを意味するとしましょう。この後、1957年から1959年の2年間は、同性愛者のデザイナーの努力により、平らな胸がトレンドになるも、ふたたび豊満派が勢力を奪還したようです。
たぶん、ここでのデザイナーとは、イヴ・サンローランのことでしょう。Aラインやトラペーズラインのことを意味していると思われます。もし、1960年にイヴ・サンローランがフランス軍に徴兵されなければ、いまのような巨乳文化の訪れを防げたかも……しれません。
おっぱい礼賛って、幼稚だと思っていました
しかし、第2章のおっぱいを讃える文学作品の列挙を読み解くのは、非常に退屈な作業でした。
なぜなら、私は昔からおっぱいに性的関心をさほど抱いていなかったからなのです。乳房や乳首や乳暈について、なんとフランス人は文学的に考察していることか。ただただ感心するばかりで、残念ながら気持ちが入っていかないのです。まったく疼かないのです。
たとえば、紹介されているヴォルテールの「処女〔ジャンヌ・ダルクを指す言葉〕」という作品。
鎧の紐がほどけ
(P276)
いま目のまえにあらわれたのは
(おお、天よ、よろこびよ、驚異よ)
ふたつの大きな乳房であった
すべらかな、半円をえがく
ふたつのひとしき乳房であった
何とその先には
目を奪う薔薇にも相似た
ふたつの小さな蕾がついていた
中二病、でしょうか。とはいえ、大真面目に女性の乳房を礼賛していた時代があったということは、それなりに興味深い。
おっぱいへの固執は、単に幼児期の口唇欲求であるとフロイト的に断定していましたが、実はそうではないということも知りました。
つまり、おっぱいはフェチの対象になりうるのです!
この歳になって、こんな発見に喜ぶのもなんですが、一部の人、もとい、大半の男性にとっておっぱいなるものは奥の深い人生のテーマなのです。
この価値観を共有できないことは、幸なのか不幸なのか。
しかし、いつの時代にも私のようなマイノリティもいることも書かれていて、すこし安心。
ナポレオン〔一七六九〜一八二一〕は女性の手足をこよなく愛していたから、乳房に対しては格別関心を示さなかった。
(P110)
おっぱいという目眩ましに騙されてはいけません
宮廷その他でおっぱいを露出したファッションが流行していたことなどを知り、ほんとフランス人は幼稚だなぁ、とばかり思ってはいられません。ロミの『乳房の神話学』に寄せたロー・デュカがこう書いています。
大衆を集団的な強迫観念にわざわざ駆り立てるという発想は、今に始まったことではない。政治にはすでに先例がいくつもある。ヴェネツィア共和国政府は、男たちを国事から逸らし、自らの権力を保持するために、「自国民」の女たちが乳房をあらわにするように仕向けたし、フィレンツェでもすでに、一八三〇年当時、同様の手が使われたのだ。
(P422)
世の男性の視線をおっぱいに集めておき、為政者はその裏で好き勝手やっていたということでしょう。刹那的に生きるのなら、おっぱいにパフパフされていたら大抵の男は幸せなのです。
しかしこれ、現代日本でなら、時の政府に都合の悪いニュースが持ち上がった際に、不思議と芸能人が薬物などで捕まってしまう現象に似ているかもしれません。一斉に国民の目をそちらに逸らすことができますから。
ということで、乳房にしろ、沢尻エリカのMDMA所持逮捕にしろ、正直あまり関心がないので、きちんと本筋の件を明らかにしてほしいと思った一冊。
『乳房の神話学』ロミ・高遠弘美訳/角川ソフィア文庫


▼パンツに興味がある方はこちら