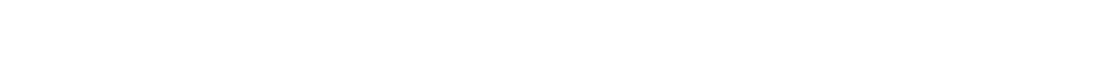連れだって歩くに最適な女性って
アメリカ合州国の大統領が、ようやく交代しました。
この4年間、日本人でもいろいろなことを感じたはずです。政治的イデオロギーなどについては、ここでは言及しないことにしているので、トランプ氏の政治手腕や思想についてとやかく言うつもりはありません。
ただ、テレビで観た、トランプ氏が大統領退任後に別荘に向かう飛行機に乗り込むシーンと、別荘のあるフロリダのどこかの空港に着陸した後、飛行機から降りるときの映像で感じた印象は、4年間変わらなかったなぁとしみじみしてしまいました。
明治期になると、華族、新政府の高級官僚、資本家といったひとびとが、上級社会をつくっていく。そして、彼らは容姿にすぐれた妻をもとめるようになりだした。身分は問わない。だが、美人であってほしい。そんな情熱が、ふくらんでいったのだ。
『美人論』
江戸期なら、とうてい玉の輿などのぞむべくもない町娘。その町娘を、上流社会に正妻としてむかえるケースが、飛躍的に増大したのである。(P66)
現代ではトロフィーワイフという言葉がありますが、つまりそれと同じことでしょう。元ファーストレディを見る度に、いつもそのトロフィーワイフという言葉が思い出されたのでした。
“夫婦げんかは犬も食わない”といいますが、喧嘩でもない他人の夫婦のことですから、正直に言ってどうでもいいのですが、メラニア夫人がどうしてもトロフィーワイフにしか見えないのです。いまや時代遅れですでに行われていないヴィクトリアズ・シークレットのランウェイを歩いていた元エンジェルにしか見えません。個人的には、バカバカしくて見るだけなら好きなショーでしたけど……。
ということはどうでもよくて、実際に、メラニア夫人はスロベニア出身の元モデルということですから、あながち遠からずなのかもしれませんが、アメリカ合衆国のファーストレディとしてどうなんだろう……と、思わずにはいられなかったのです。スノッブな上流社会からいろいろ批判されるんじゃないかと。
日本の明治期においても、伊藤博文をはじめ芸者上がりを正妻にしている政界・財界人は多いのです。武家社会なら、正妻は奥様と呼ばれていたように、社交の場には出てくる必要もなく、文字通り家の「奥」にいればよかった。
しかし、文明開化後はそうもいきません。欧米のように正妻も社交の場に出ていかねばなりません。つまり、容姿端麗で酒宴の席でも立ち回れるコミュニケーション能力の高い女性、つまり芸者さんが選ばれたというわけです。
彼女らは、士農工商というヒエラルキーが解体した象徴でもあったでしょう。でも、もともと社交界で多数を占める高貴な出の女性たちからは、かなり冷遇されていたようです。たぶん、メラニア夫人もそうであったに違いありません。
自由と平等の国、USAのファーストレディとしては、ある意味において象徴的であったとも言えるメラニア夫人。ただ、夫であるトランプ氏にかなり問題があったことを除けば。
美人も、企業内だと、美貌を売るというわけにはいきにくい。収入も、社内では他の女子社員と同程度のものしか、期待できないだろう。だから、美貌を売りたい女は、よりペイの高い看板娘の外注産業へとながれていく。(P282)
『美人論』
生まれ持った美人ならば、それを強みにして生きることに、なんの問題があるでしょう。自分の美貌をより高いペイの所に売りつけるという意味においては、ファーストレディは、その最たるものなのかもしれません。
死別もしくは離婚しても、こうした「箔」のついた女性には、一定の需要があるのです。元ケネディ夫人やダイアナ元皇太子妃のように。まさか、自分の夫が大統領になるなんぞ夢にも思っていなかったでしょうが、先見の明があったとも考えられます。あとはどのタイミングで……。
客観的な美人って、なに?
さて、今回の文庫は、タイトルにだまされてはいけません。美人の普遍的なカノンなどについては、一切触れられていません。どちらかと言えば、女性の社会的地位の変遷を、「美人」という概念を柱にして描き出した書です。
明治以降の多くの書物や雑誌などからの引用を用いて、その時代に女性がどのように評価、扱われていたか、また、女性たちの意識がどうであったかを分析しているので、退屈せずに最後まで読み通すことができます。
その引用に、1989年の雑誌の文章があり、女性学者として伏せ字になっているU・Cさんというのが、すぐに上野千鶴子さんだと分かったのですが、当の本人がこの文庫のあとがきを書いているという事実に、痛快さを覚えてしまいました。
このあたりの引用を要約すると、フェミニズムの女性学者U・Cさんのことを美人と評する雑誌に、林真理子が噛みつくというモノです。彼女にしてみれば、あの程度で美人と評されるのなら、私も美人作家だ、とでも言いたかったのでしょう。ここで、どんぐりのなんとか、などと一刀両断してはいけません。
この林真理子の怒りを、評論家中野翠が慰めている一節も引用されているのですが、中野翠の慰めの言葉を意地悪く要約すると次のようになります。
1)女性にはいろんな職業がある。
2)それら職業別に美人の競争率がある。
3)モデルや女優は、美人の競争率がもっとも厳しい。
4)競争率が低いのは、文筆業界とアカデミズムである。
5)だから、林真理子も文筆業界では美人である。
6)しかしもっとも競争率の低いのは、実はアカデミズムである。
7)だから上野千鶴子もアカデミズム業界では美人である。
以上のことから導き出されるのは、アカデミズムよりも競争率の高い文筆業界の美人である林真理子の方が上野千鶴子よりも美人である……って、ほんとうにどうでもいいことなんですが……。
容姿がどうのというより、どちらも執筆業がひとつの生業なのですから、作品の出来不出来、面白い面白くないだけが私にとっては重要なので、本当にどちらが美人であるかは問題ではないのです。しかも、美人の基準って、そもそも曖昧なので、美人だと言ったもん勝ち的なところがあります。
不健康から健康へ、白痴から知性へ、怠惰から勤労精神へ。美人の属性は、両大戦間期をさかいに、そううつりかわってきた。(P192)
『美人論』
つまり、美人のカノンってどこにもなくて、都合のよいようにつくられているということです。そして、それはこの文庫でも指摘されていますが、いまや美容産業のコマーシャリズムに大きく左右されているのです。
輝いている女性は美しい、的な。
みんなそれぞれ美しい、的な。
ありのままで貴女は美しい、的な。
つまり、もはやこの世にブスは存在しません。
だから、一瞬も一生も美しくいようね(死ぬまで当社の商品を使い続けて下さい)という強迫観念。
というわけで、幼い頃から親しんできた本や絵画などから、知らぬ間に刷り込まれてきた結果でしょうが、好きな女性のタイプってブレていないことを再確認した一冊。
『美人論』井上章一/朝日文芸文庫