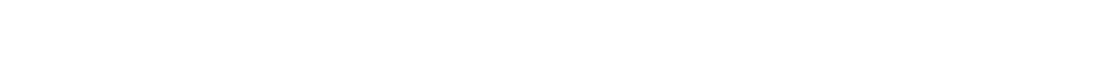最近のマイブームは1970年代の邦画
先日、映画『十九歳の地図』をAmazonPrimeで観ていたら、主人公の予備校生吉岡が小脇に抱えている英和辞典が、高校生の頃に使っていたのと同じだったので、懐かしい気分になりました。
原作の中上健次の小説は、高校生の頃か大学生の頃に読んではいるのですが、まったく中身を覚えておりません。映画化されたのが1979年なので、自分が小学2年生くらいの東京都北区の景色が、これほどまでに『ALWAYS 三丁目の夕陽』やマンガ『タイガーマスク』や『あしたのジョー』の世界観に近しいことに、まずは驚いてしまいました。
なぜなら、その10年後には、映画の舞台に近いところに移り住んでいたし、映画に登場する代々木ゼミナールには通っていたわけなので、映画の中で見るあまりにも遠い遠い昭和の世界が、実は、とっても身近なところであったからです。
さて、映画のレビューではありません。劇中で主人公吉岡が使っている「新英和中辞典」は、黄緑色の函(はこ)が特徴です。函から出すと、表紙は濃い臙脂色に近い茶色とでもいいましょうか。高価な革製ではなく、塩ビ(?)の廉価版表装ですが。
劇中で使われた辞書と、私が使っていた辞書は、おそらく違う版です。映画で使われていたのが、最も新しい版であれば、1977年の第4版。1985年には第5版となっているみたいなので、私が使ったのはこの第5版だと思われます。
そこで、ちょっと気になったのでネット検索してみたら、第2版が1967年、第3版が1971年となっています。映画を観ても分かるように、東京の景色(というより日本の風景)は、戦後に目まぐるしく変化しました。その変化に合わせるかのように、英和辞書も時代にそぐうものへとブラッシュアップされていたのです。
乱れているという方が乱れている
でも、そんなに頻繁に英単語の語釈って、移ろうものなのでしょうか。
その答えが、この文庫にあります。「新英和中辞典」ではなく、「三省堂国語辞典」の編集委員による一冊です。
説明しようとする対象を、できるだけ自分の目で見、耳で聞き、舌で味わい、指で触れる。そのことに、興味を失ったが最後、私は、実感のこもらない、魅力の乏しい語釈しか書けなくなるでしょう。(P204)
『三省堂国語辞典のひみつ 辞書を編む現場から』
あえて大袈裟に表現すると、「言葉は生きているのだから、時代によって意味が変わってもいいんだ!」という言葉の乱れ肯定主義と、「美しい日本語を守りましょう、言葉の乱れは許しません!」という明治時代以降の関東方言絶対主義のどちらが正しいか、ということがよく議論されます。ここでは、そのどちらが正しいのかをジャッジするわけではありません。
たとえば、「全然」という単語は、若者の間から強い肯定に使われるようになったと考えている人が多いと思います。本来的には、否定的に使われなければいけないと。
たとえば、「全然よくない」はオッケーで、「全然いいじゃーん!」はダメ〜的な。
でも、「全然〜非定形」というのは、実は戦後に一般化したもので、もともと肯定形で結ぶのも「全然」ありでした。漱石の『坊ちゃん』や芥川の『羅生門』にも、肯定形で結ばれる文章で使われています。
こうしたこと知らなくても、会話や文章中に「全然」が出てきたとき、前後の会話や文章から、その意味を間違って捉える人は少ないはずです。意味が通じるから、別にどっちだっていいじゃーん、じゃなくて、きちんとジャッジし示してくれるのが辞典・辞書なのです。だから、国語辞典編纂者である筆者は、常にナマの言葉に接して、その意味や用法などを丁寧に吟味する必要があるのです。
言葉が乱れている、と糾弾されても、実は常識だと思っていた方が乱れていた言葉だった……ということも、実際にあるのですから。
外出自粛で興味が薄れる今日この頃
さて、辞典編纂者と同じく言葉を使う編集者の場合においてみましょう。書籍ではいないと思いますが、雑誌、WEBに関わらず編集という生業に携わっている人間で、本(活字)を読まないという人が、実は多いと云う事実を、実際の現場で知りました。
ずいぶん昔ですが、私が担当していた雑誌ページの文字校正で、「玉に瑕」という単語の「瑕」に、赤ペンの引出線で「キズ」と赤字が入っていました。その文章を書いた筆者が、「玉にキズ」とは表記しないのは明らかですし、カタカナにした時点で、その筆者の文章の視覚的リズムが台なしになることが分からないのです。
赤字を入れた編集者に理由を尋ねると「漢字を読めない人が多いから」というものでした。ならば、ルビを入れて解決すべきです。
しかし、この文章の持つリズム(視覚的、語感的)であったり、行間を読むなどと云うことは、実際に多くの文章を読むことで培うものです。なぜなら、言語はそもそも後天的なものですから。
編集者だけでなく、雑誌・WEB周辺のライターというものも、さらに輪をかけて言わずもがな。つまり、そういうライターと編集者の組み合わせで世に出てしまった文章は……(以下自粛)。
頂いた原稿を、ひととおりさしさわりのない日本語に変換するというブルシット・ジョブのために時間を費やすのって、もうこの歳だと本当にツライのです。学生の小論文添削ならやりがいを感じられるかもしれませんが、こちらは原稿料を支払っているわけですから、添削料とトレードして欲しいくらいです。
最近は、そんな気の遠くなるような作業から開放されるために、気心知れた特定の執筆者にしか原稿発注しなくなってしまいました(なので、いまお仕事ご一緒させていただいているみなさま、どしどし原稿送って下さいませ。雑誌と違ってWEBには紙幅というものがありませんので)。
……という、私の愚痴はどうでもよくて、文章の最小パーツである単語の意味でさえ、編纂者はフィールドワーク──実際の現場で説明しようとする対象に対峙しているわけです。それくらい単語ひとつひとつが大切なわけですから、それらが織りなして出来上がる文章というものは、さらに実地で対象と向き合わなければ、人の心に届く文章にはならないでしょう、という拡大解釈が今回の趣旨となります。
そういえば、『十九歳の地図』の予備校生の主人公吉岡が、新聞配達&集金中、気に食わなかった家には、地図に「✕」印を描き入れていたことも、「自分の目で見、耳で聞き、舌で味わい、指で触れ」て得た結果でした。
編纂者の飯間浩明氏は、こうしたことに、「興味を失ったが最後、私は、実感のこもらない、魅力の乏しい語釈しか書けなくなるでしょう」と書いています。
最近、テレワークを続けていて、ふと、アレに対して以前ほど興味がなくなっていることに気がついてしまいました。趣味としてのアレはもう、極みまで見てしまった&やり尽くしたがために、興味が半減してしまったのかもしれません。
ならば、書く対象を興味あることにスライドすればよいだけのことですが、コロナ禍という現状において、「自分の目で見、耳で聞き、舌で味わい、指で触れる」ことは、なかなかムズカシイことになってしまいました。
未然形のないが全然ないと融合!?
ところで、小学生か中学生か、いつだったかは記憶にないのですが、「全然」は非定形で結ぶと習った覚えがあります。どうして戦後に非定形で結ぶことになったのか、そしてそれを不思議に思わなかったのか。
ひょっとしたら、国語の文法の授業で習う「未然形」が影響しているのかもしれません。未然・連用・終止・連体・仮定・命令のアレです。
動詞の活用の見分け方は、未然形で決まります。動詞に「ない」をつければ、五段活用か上一段活用か下一段活用か、分かるようになっています。
たとえば「見る」、「聞く」、「味わう」、「触れる」という動詞に「ない」をつけると、「見ない」、「聞かない」、「味わわない」、「触れない」、となります。つまり、これら4つの動詞は順に、上一段活用、五段活用、五段活用、下一段活用と云うことが分かります。
この「未然形」=否定の「ない」をつける、というのが、「未然=否定・ない」から「未然・ない」となり、なんとなく「全然ない」と頭の中でブレンドされて、「全然」は「ない」とセットであると定着したのではないでしょうか。
今回、そもそも動詞の五段活用って、なんだっけ? ぐらいにしか覚えていませんでした。使わない知識はそれくらいアバウトで曖昧模糊となって、いろんな記憶と溶け合っているのです。「未然」と「全然」と「ない」という文字が、頭の中でグチャグチャにつながってもそれもありなん、なのです。
ということで、やっぱりきちんと言葉の意味を定義してくれる国語辞書って、いつの世にも大切だな、ということが分かった一冊。
「かろかつくいいけれ」と「だろだつでにだななら」って、どっちが形容詞で形容動詞でしたっけ?
『三省堂国語辞典のひみつ 辞書を編む現場から』飯間浩明/新潮文庫