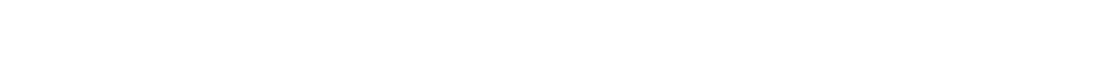文章にもある適材適所
雑誌にかかわらず、メディアに執筆する際にはそのメディアにあった文章というのが必要となります、当然ながら。
先日、尊敬する二十代の頃からお仕事をご一緒させていただいている方と、自動車評論に関してある話題があがりました。
それは、自動車のインプレで、「私にはとうてい買えるような値段ではないが」という内容から始まり、「仮に購入できる余裕があっても買わない」という感じで終わる文章です。
この手の文章って、インプレ原稿の中でまったく意味がないよねー、という話で盛り上がりました。
大抵の場合、こうした文章が書かれるクルマは高級車ということになるのですが、富裕層メディアに寄稿していたとしたら、そもそも高級車がなんたるかを分かっていないことが露呈してしまうと同時に、まったく読者目線になっていないことにも問題があります。
つまり、ターゲットとしている読者が読んだ際にまったく有益な文章になっていないばかりか(なぜなら、そうした高級車を普通に購入する人たちだから)、そのメディアのブランディングも下げてしまうことになるからです。世界観やストーリーが丸潰れです。
では、中綴じB5版雑誌のような大衆メディアならば大丈夫なのか? 庶民派としてのインプレッションになるのでしょうか。結論としては、やはり無用な一文であることには変わりありません。
スーパーカーをはじめラグジュアリーなクルマは、「走る・曲がる・止まる」という出来の良し悪しだけではジャッジすることができません。「この値段でこんなもん?」的なジャッジは、書いた本人の「分かってなさ」を露呈することになるのです。
G-SHOCKならば、氷上でパックの代わりにスティックで思い切りシュートしても大丈夫でしょうが、何千万円もするスイスあたりに本拠地のあるブランドの腕時計ならば、一発で終了です。つまり、価値基準が全く違うのです。耐久性やタフさという価値基準で語る時計ではないということです。所有することそれ自体に意義あるものですから。
もちろん、多様性が尊重される昨今ですから、いろんな視点のいろんな批評があっても構わないのですが、それは個人のSNSやブログで発信してね、ということです(編集者目線で言わせて頂くと)。
では、こうした場違いな原稿は、書いた執筆者に責任があるのかといえば、そうではありません。それは編集者にあります。執筆者の原稿を活かすも殺すも編集者──エディターの采配ひとつに掛かっています。
「編集者は、芸人でなくてはならない。ひとつおぼえの芸で商売するのは、プロのやることではない。客の注文におうじて、いつでも自在にさまざまな芸でこたえられるのが、ゼニのとれる芸人だというのなら、編集者もそうあるべきだ。硬質の文章も書けると同時に、漫談のような軽いタッチで書くテクニックも身につけている。そのくらいの芸ができなくてはダメだ」
花森安治の編集室「暮しの手帖」ですごした日々(P191)
これは、花森安治氏が語った言葉として文庫の中で書かれています。
アカデミックな出版社から大衆的な出版社に移った20代の頃、当時の上司に「雑誌編集者は、ジャーナリストではなくてエンターテイナーだ」と言われたのですが、自分もまさにその通りだと思っていたのでカタい出版社からやわらかい出版社に移ったのでした。
そして、面白いと思うことを雑誌の企画や、まるごと一冊の雑誌として作ったのです。
ジャーナリズム、ではない商業雑誌
しかし、クルマ業界メディアの編集者、ジャーナリストと言われている人たちの中には、商業誌での振る舞い方(原稿の書き方)が、分かっていない人もいます。本当にジャーナリスティックに自動車を評価したいのなら、アゴアシつきの試乗会でチョイ乗りするのではなく、身銭を切って購入するしかありません。
だから、花森安治は『暮らしの手帖』で、自動車のテストは一度も行っていないのです。もちろん、金と時間がかかるということが、当時のネックだったかもしれませんが、クルマってどうしてもあるところから日用品ではなくて嗜好品であったりもするので、クルマというジャンルでひとくくりにして、庶民のために評価するのも難しいものがあります。
話は脱線してしまいましたが、花森安治のいう編集者というのは、編集記者ということなのでしょう。もちろん、自分では記事を書くことはなく、執筆を依頼することが主である編集者もいます。しかし、その際に媒体に合わせて執筆者をうまく使い分ける、もしくはうまく書かせるという芸当がなければダメです。
タイトルや見出し、リードなどは編集者が書くことの方が普通なので、もちろん、自在にさまざまな芸を身につけておくことはいうまでもありません。
仕事道具は自分で自分専用を揃えることの大切さ
編集部員には、自前でそろえなくてはならない道具が、二つありました。カメラと小型テープレコーダーです。編集者にとって、どちらも欠くことのできない道具ですが、それはあくまでも自前でなくてはならない──ここにも花森安治の、職人の親方らしいかんがえかたが底流していたとおもいます。
花森安治の編集室「暮しの手帖」ですごした日々(P118)
安藤忠雄だったか記憶は定かではありませんが、著名な建築家の事務所では、筆記具をはじめとする文房具などは自前で揃えるというのをテレビで観てとても共感したことがあります。
自分も、編集者として必要な文房具、カメラ、ICレコーダー、MacBook……などは、すべて自前で揃えていました。フィルムを使っていた時代、ポジ袋は編集部で用意したモノを使っていましたが、ダーマトはステッドラー、ルーペはPEAKのものを自分で購入して使っていたという具合です。
カメラやICレコーダーを個人で持っていない最近の若い編集者を見ると、時代も変わったなぁという気がしてなりません(まあ、スマートフォンですべて事足りますが)。編集という仕事が、職人気質ではなくなっているのでしょうか。
ただし、編集者としてのものを見る眼は鍛えられないとも思うのです。持って生まれた自意識が高いのも結構ですが、鍛えるべき美意識はいつまでたっても高くならないと思うのです。なぜなら、自分の仕事に対する思いの入れようがまったく異なると思うからです。
自動車のメカニック、それに大工……などなど、自分の道具・工具を持ち、大切に扱っている人の方が腕がよいというケースをよく見かけます。弘法筆を選ばず、とも言いますが、それはごくごく一部の神がかった選ばれし人たちにあてはまることで、凡庸な編集者には所詮無理な話なのです。
ということで、ゼニの取れる編集者になるには、ジャンル問わずいろんな本を読み漁って、いろんな文体やレトリックを吸収するのが早道だということが分かった一冊。読書しない編集者(あと執筆者)って、やっぱり信用できません。
『花森安治の編集室「暮しの手帖」ですごした日々』唐澤平吉/文春文庫